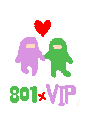中央公園には風車がある。どこか遠い国の粉挽きを模した風力発電機だ。
彼はしばらく周りを歩き回り、立ち止まると今度はしゃがみこんだ。
懐から小さな端末を取り出すと、目の前にかざす。ファインダーの先に風車が回っている。その後ろの林に、ちらりと光があった。
その光が大きくなり、風車に激突して破壊する場面を想像する。
風車が壊れたところを見たことはないが、描かなければならない。
堂仁はようやくシャッターを切った。
ドン・キホーテを忘れたいと堂仁は思う。それは矢追を忘れたいと思うことと等しい。
自分に根を張った存在を、引きはがして身軽になってしまいたい。
はがしたら自分の心はどこへ行くのだろう。
「これはなんですか」
台の端にぽつんと置かれたビニールポットに注視され、年配の夫人は面映ゆそうに破顔した。
「アボカドなのよ。……あのねえ、わたし今年小学校に上がった孫がいるの」
唐突に始まった孫の話に、男は眉一つ動かさず相槌を打った。
「その子が食べた後のアボカドの種を自分で一年間育てたものなんだけどね、今朝『おばあちゃん、これ売ってお金持ちになってね』ってさ」
大玉の菊ばかりが並ぶ台の向こうに、咲き誇る花に負けない笑顔がある。
彼は飼い犬を伴っていつもの散歩コースにやってきていた。
いつもとは違う辺りの様子に大喜びし、背後で行き交う人に愛想を振りまいている愛犬の尻尾が男の膝裏をはたき続けている。
「いくらですか?」
彼はわずかに頬を緩め、財布を取り出した。
中央公園ではフリーマーケットが開かれている。
「わたしのではない彼は左利き」
彼女は思い切りボールを投げる。見失ってもいいのだ。
「幾何学」
「頸城」
「帰宅」
「茎」
「気楽」
「空気」
「客」
「籤引」
「金額」
「空即是色」
「」
彼女はまたボールを見つける。今度は目をつむって投げる。