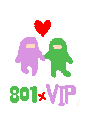「夜の街明りって変な気分になるなあ」
固いシートの上で窓の外を眺める。赤信号に軋みながら車は停車し、矢追の頭がカクンとつんのめった。
堂仁は何をいうでもなく窓を少し下げ、胸ポケットから出した煙草に火をつける。
「一本くださいな」
差し出された箱から引き出した。百円ライターの火は心許無い。
浅く吸い込むが美味くも不味くもなかった。
そういえばこんな味だったような気がする。
車が動き出し、対向車のヘッドライトに矢追は目を閉じた。
揺さぶられて意識が浮上する。うつらうつらしていたようだ。始めは妙な揺れに体力を消耗したものだが、慣れとは不思議なものだ。「起きろ」
「ごめん」
古びたアパートの駐車場には砂利が敷いてある。堂仁は錆びた鉄階段を足音を立てずに上る。矢追にはできない芸当だった。
部屋は綺麗に片付いていた。
「お邪魔します」
言うなり矢追はベッドに潜り込む。かすかに煙草の香りがする。
「何だよ」
「なんか落ち着く」
「馬鹿だろお前」
心底呆れた口調で堂仁は言った。
堂仁は端末を起動し、オーディオでサティを流す。
矢追はサティを知らない。
「堂仁、腹減った」
「キムチ鍋だな」
堂仁のタイピングは備府に勝るとも劣らない。
「あんまり辛くしないでよ」
「お前が子供舌なだけだ」
「堂仁が辛党過ぎるだけだと思う」
備府が出会った時に食べていたのもキムチヌードルだった。
ベッドの上で漫画を読む矢追は備府との出会いを拾い集めるように思い出している。
もしも初めて会った時友人になっていたら。
友達を紹介せず、サークルに誘わず、来野に引き合わせなかったとしたら。
「備府を独占する」という妄想は、限り無く不毛で甘やかだった。