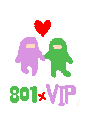ありふれた話だと岡は思っている。
あるところに男がいた。男はうんざりして白い手で片頬を覆っている。それが向けられるのはこの状況であるし、熱と湿気を孕んでいる相手の眼であるし、そもそもの原因である自分のだらしなさでもあった。
「もういいでしょう」存外深く口の中を切ったらしく、思わず血液混じりの唾を吐く。相手は、食いしばった奥歯の隙間から馬鹿にしやがって、と絞り出した。
これはずいぶんと腫れるだろう。
あの人に心配されてしまうだろうな、と岡はため息をついた。
ありふれた話だ、と
岡は思っている。自分にのしかかる男を眺めながら、一番疲れない方法を模索している。
知っていたわけではないのだから、弁解すべきだったろうか。
どちらにしても、男は岡に手を上げただろう。
自分の女の浮気相手が自分の浮気相手だった、とうわ言にも聞こえる真実を突き付けられた男はどこか途方に暮れたような顔をした。
「わざとじゃないんです」
岡はわざとのんびりと言った。女はとっくに逃げ出した。かわいい八重歯が無事でよかったと岡は思う。
わざとでたまるか、と男はうめく。
「いつからなんだ」
「今日が初対面です」
彼女は酒が入った席での与汰話がいたく気に入ったようだった。このままではピロートークも怪談になるのではないかと懸念していたところだ。
特に飢えているわけではなかったが、ぐずぐずしていたせいでまたとない機会を失ったともなれば、手近なホテルに連れ込むべきだったと悔やみもする。
「これから映画を見るところだったんです」
映画を見ながらの予定だったんです、と言わなくても通じたようだった。男は怒りを持続させるのに苦労しているらしい。膝から乗り上げ岡を押し付けていたベッドから体を起して胡座をかいた。周りに散らばったディスクのパッケージはほとんどが赤と黒を基調としている。
ホラー、スプラッタ、サスペンス、ホラー、ホラー。
男は思い出したようにディスクをはたき落とす。
カーペットのせいでほとんど音はたたない。
「どうします?」
最後に誘う程度には自分はこの男を気に入っていた、と岡は思う。