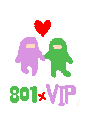彼女が食べるようになったのは、目覚めてから二十日も後のことだ。ベランダに置かれたケースの中に、彼女は五カ月眠っていた。指先で摘まんだ特大粒の配合飼料を見せると、ぱっかりと口が開く。その下あごに乗るよう俵の形の粒を放り込むと、彼女は首をひっこめ、水と共に飲み込む。また首を伸ばす。口を開ける。内部は鶏ささみに似た色だと思う。あんまり長い事そう思っていると、彼女は餌を指ごと口に入れる。
彼女には決まった名前がない。初めの二週間、彼女はカメと呼ばれていた。それがカメ吉になり、カミィになり、ここ最近はメーちゃんと呼ばれている。どのような呼びかけに対しても彼女は鼻さきを和田に向ける。松の葉を煮詰めたような深いみどりの甲羅はつるりと滑らかで、てんでんばらばらに水をかくぽってりとした脚の先には羽軸根を思わせる爪が揃っている。尻尾はすんなりとして、甲羅に沿わせると半周して首まで届くほどだった。その首から目の周りまでひすい色の斑点が続き、濃灰の肌によく映えている。この地域ではよくみられる沼亀の一種だ。
しかし和田にとって彼女は特別な、世界一美しい亀であった。和田が以前住んでいた町にも亀はいた。それは砕いた岩を張り付けたような足で道路を横断する亀であり、生垣のハイビスカスをむしり食べてしまう亀であり、砂場にやってきては山を崩しにかかる亀であり、つまり陸亀であった。それも天然記念物に指定されたなんとかゾウガメというやつだ。我が物顔でそこらじゅうにいるカラカラに乾燥しきったその亀と町とが嫌で、ここに住むことを決めた。どうせすぐ帰ってくるに決まってる、地元の連中はなぜかそろってそう言ったが、和田の決意は梅雨時の布団裏に菌糸のコロニーを発見した日にも揺らがなかった。ここに住んでもう一年になる。彼女は満足したらしく口を開かなくなった。それでも円らな目はこちらに向いている。ゆっくりと人指し指を近づけるとペトリと鼻をおしつけてくる。機嫌がよいようだ。
夜明けの空はよく晴れている。ギシャギシャとガラス戸が開く音がして、となりのベランダに人が出てくる。和田はとっさに部屋に戻ろうとしたが、そもそも自分がここにいるのは隣人のせいだと思いなおして知らぬふりを決めた。ずずっと鼻をすする音がして、そのあと溜息が聞こえた。
「あの……和田さん」
「……はい」
和田は仕方なく返事をした。隣人は舌が痺れているかのような、わずかにもたつく話し方をする。
「あの、沢村です。昨晩は、大変ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした」
いえ、とかまあ、などと口の中で転がしていると、隣人はまた少し息をついた。二人の間には仕切り板があり、『非常の際はここを破って隣戸に避難してください。』と書いてある。
「近々引っ越しますので、またご挨拶にうかがいます」
「はあ、大変そうですねえ」
となれば、静かな夜は戻ってくるのだ。気のない相槌を打ちながら安堵した。沢村の声は昨日の朝のゴミ捨て場での挨拶と変わらない。一晩泣き続けられる喉は特別強靭なのだろう。マラソンが得意そうだと和田は思った。
それじゃあ、と結局顔を合わせないまま沢村が去ると、和田はもう一度ケースに目を落とした。彼女は水底に沈んでいる。二度寝しようか。それとも賞味期限が昨日までのおにぎりを煮て食べようか。和田もベランダを去った。
水を吐くと海苔の滓が洗面台に広がる。血の味もする。昨夜は散々だった。和田は一人ではなく、やっとの思いで招いた斎藤と、映画の観賞会をしていた。
画面の中で主人公が潜入捜査をし始めたころ、隣からの話し声は怒鳴り声になった。斎藤が身じろぎもせずに映画を見続けているので、和田は斎藤の髪の隙間から出ている白い耳を見続けた。斎藤の耳は横に広がるようについているので、滝をわける岩のように髪の毛をかきわけている。主人公が敵のアジトを爆破するころには沢村の修羅場もクライマックスを迎え、悲鳴や何かの割れる音がしている。和田は貧乏ゆすりをしながら斎藤の耳がうっすら赤くなっているのを見つめる。爆破シーンが終わると斎藤は立ち上がり、このアパート和田くんとおとなりしか住んでないの?と聞いた。え、そうだよ。わかった、じゃあ帰るね。
ガシャーン、また何かが割れ、斎藤はほぼ仁王立ちで和田をねめつけている。画面では主人公が恋人と熱い抱擁を交わしている。あ、うん、そのほうがいいね。あの、あぶないし。和田は上目遣いだ。斎藤は鼻から息を吐くと、玄関に向かい、靴を履いた。ドアが素早く開き、素早く閉まったのであわてて追いかけると、斎藤はアパートの駐車場のカーブミラーの下で待っていて、右手を差し出した。和田はほっとするが、それに気付いた斎藤は再び鼻から息を吐いた。斎藤の家は歩いて十分ほどのところにある。古くからの土地持ちが多いこのあたりでも、斎藤の家は別格に大きかった。敷地には三軒も家が建っている。斎藤の兄弟の家族が住んでいるらしい。
気をつけてね。警察呼んだ方がいいんじゃない?ああ、うん。どうなったかあした聞かせてね。あした?うん、あした部活ないから。わかった。あした部活なかったんだよ!わかってんの?ご、ごめん。あさっては部活あるから。うん。じゃあね、あっそうだ、おじゃましました言うの忘れてた。
実は沢村の部屋にはすでに数回警察が来ている。和田ではなく、近隣住民の通報によるものだ。そのたびに次の日沢村一人が謝りに来る。今夜は今までで一番激しかった。帰るころには警官が来ているだろう。和田はわざとコンビニに寄った。目に痛い灯りのもとで青年漫画誌を立ち読みし、読み切らずに買って帰る。予想は外れたらしく、アパートは静かだった。和田は自分の部屋に入ろうとしたが、思いなおして沢村の部屋の前に立つ。玄関脇の小窓から灯りが漏れていた。インターホンを押そうとした瞬間勢いよくドアが開き、和田はしたたかに鼻を打った。あまり鼻が高くないことが災いしたのか、上唇も切った。沢村の相手を見たのは初めてだった。和田を押しのけ、飛び出していく。想像していたより若い女だった。
「それで?」
「それで、おとなりさんはぐっちゃぐちゃの部屋の中にいてさあ、泣いてるんだよ」
「うん」
「大丈夫ですか?って聞くじゃん?そしたら急にびしっとして『大丈夫です。本当にごめんなさい。少し放っておいてください。ごめんなさい』って言って立ち上がって後ろ向いたのよ」
斎藤は自分の爪を見ている。あんまりずっと見ているので、和田は自分が喋った言葉がテロップになって爪に映っているんじゃないかという気がし始める。
「あー」
「そしたら髪の毛がばっさああああってなって」
「髪の毛長いんだ」
「もうすごいの、ふくらはぎまであんの」
「えっ?立ってて?」
斎藤がやっとこっちを向いたので、和田は一層饒舌になった。
「そう!立ってて。最初かつらかなんかだと思ったんだよ。でもちゃんと生えてんの。普段おばさんぽい団子にしてるんだけど、どんだけ圧縮してたんだって感じ」
「ちょっとそれ怖くない?」
二人は歩きながら会話している。歩いているのは恋川公園だ。一級河川である大川にそそぐ小さな川で、三キロにわたって川沿いが整備されている。
「いや、びびってちょっと泣きそうになった。でもそのうち引っ越すらしい」
「なんか怖いよ……宗教の関係とか?」
「あーありえるかも」
恋川公園は大川の二番土手にぶつかって終わる。二番土手の向こうには広大な水田が広がり、そのまた向こうに一番土手がある。大川はその向こうだ。
「今日はさ、一番土手に行こうよ」
「和田って土手好きだよね」
「土手っていうか、ここらへん全体的に好きだよ」
斎藤は右目をこすった。和田はメーちゃんを思い出す。
丸岡と初めて出会ったとき、沢村は店員で丸岡は客だった。沢村の髪の毛は腰までの長さだった。地主が趣味で開いている小さな手芸店で働き始め、まだ慣れていないころだ。
「いらっしゃいませ」
ドアベルが鳴り終わる。初めて見る客だ。つばの広い帽子をかぶっている。沢村は奥歯に力を入れた。沢村にはいくつも癖があるが、これは自覚しているうちの一つ、心の準備をするときの癖である。
客はまっすぐリボンの棚に向かった。そろそろマスキングテープの新作を出さなければ。そう思っていると、
「ね、君」
と声がかかった。客は一人だ。
「パールとリボンでアクセサリー、作ろうとしてるの。いっしょに選んでくれない?」
華やかな見た目で予想したよりも低くやわらかな声だった。来たぞ、と沢村は身構える。
ときたま越えなければならない、常連奥様による新人チェックだ。
「へえ」
沢村の口から出た返事は、二人を見つめあわせる効果があった。
「失礼しました、あの、はいって言おうとしたんですけど」
ぱちくりというのがぴったりな様子でまばたきした後、客はにやりと笑った。
「どこの江戸商人かと思っちゃった」
言い終わるとすでに穏やかな微笑にすり変わっている。
「こっちに来て。どれがいいかしら」
「やはり光沢があって色の深いものが合わせやすいかと思います。こちらなどいかがですか?」
「そうね、でも私紫は似合わないのよ。君は何色が好き?」
「私は群青が好きですね」
客はカラカラと群青のリボンを引き出した。綺麗に磨かれた爪はずいぶん短く切ってある。群青のラインはどんどん伸びていく。とうとう腕をいっぱいに広げる。
「ね、足首見せて」
「は、」
「足首よ」
客は片膝をついてかがみ、沢村のスラックスの裾をまくりあげるとリボンを足首に巻き付けた。
「予想が外れた」
ぶっきらぼうに言って、動けないでいる沢村を見上げる。
「へ、」
「君鈍くさいから、もっと太いかなって」
丸岡はアキレス腱のくぼみを親指で押した。
「馴れ初めそんなんかあ。それじゃあ、さわちゃんは俺が金持ちになっても愛人にはなってくれねえなあ」
「どういう意味ですか?」
耳下から髪を三つ編みにしながら沢村は聞いた。柘植の櫛の彫を指先でたどりながら、うなぎ屋は陶然と真っ黒な流れを追っている。
「この髪も奥さんに言われて伸ばしたんだろう」
「そうですよ。君にはロングヘアの才能があるとか言って」
「才能、そうそうそいつだ、とにかく生まれついての資質っていうのはどうしようもないんだよ」
伸びる速さ、髪の寿命、量、強さ。全部そろわんとこうはならないからね。先細りがほとんどない上にここまでのストレート。二十年前の俺に教えてやりたいね、お前が真面目にがんばれば超長髪のお姫様が現れるぞって。うなぎ屋は編みあがった右のおさげを手に取るとうなりだした。
「触りたい触りたいと思ってはいたけど、複雑な気分だねえ」
「もともとこだわりがあって伸ばしていたわけではないので……手入れも自分ではあんまりしなかったな」
「おうそうそう、その手入れの話をしてくれや。上乗せするからさ」
臨時休業のうなぎ屋の座敷に二人はいる。引越しの挨拶の順番を後回しにしたのも、櫛を持ってきたのもその気があったと言えなくもない。しかし店を休みにするとは予想外だった。
丸岡と付き合い始め、最初に連れてこられたのがこのうなぎ屋だ。一番土手と二番土手の間、水田のただ中にぽつんとある。江戸時代から続く老舗らしい。このあたりはもうとっくにうなぎはとれなくなっているので、継ぎ足し継ぎ足しの秘伝のたれと、どこか遠くのおいしいうなぎを使っている。
「あの人は、洗うのが一番好きでしたね」
まず荒歯の櫛で毛先から梳いていく。髪を傷めないように、じれったくなるほどゆっくりと。櫛を細歯のものに持ち換える。頭皮をたどり、うなじをかき上げ、流れを揃えていく。
「それから?」
うなぎ屋は沢村の真横に座布団を枕にして寝転がった。身じろぐたびに揺れる、ふりそそぐさまを飽きもせず注視している。上映中のプラネタリウムで探しても、こんなに輝いた瞳はそうそう見つからないだろう。触ってもいいですよ、と促すともったいないとかなんとかぶつぶつ言っている。
それから、椿油を塗りたくる。髪がずしりと重みを増して、髪は寄り集まって体積が減る。それを薄く広げ、両手で挟んで撫でおろしていく。ふと手が止まる。指でまさぐり、摘まみ出したその一本は結び目が出来ている。
「はー、こんだけ長いと一本でも絡まるってことかい」
手の動きも水の流れも常に一定方向に。洗ってすすいで、それから乾燥。
「時間はどれくらいかかんの」
「フルコースの時は二時間くらいですかね」
「それがなくなるのか」
「楽しみで仕方がないです」
沢村はリクエストに応え、ポニーテールにとりかかる。高い位置で結び目を維持するのは至難の技だ。
二番土手を登ると、和田は歓声を上げ、数回飛び上がった。苗植え前の水田に水が張られている。藁色の枠の鏡を敷き詰めたようだ。
「すごいよ、ほら」
「そうだね」
「ここは水がいっぱいでいいよなあ。俺が前住んでたところは取水制限があってさあ」
「未だに朝シャンすると感動するもん、でしょ?」
「ばれたか」
自転車が迫っていることに気付き、和田は斎藤に手を伸ばした。斎藤は体をひねる。
「何?」
「自転車来てる」
「ああ」
斎藤は和田の手を取らない。
「いけ!サンダービーム!」
「そうはいくか!ハイパーバリア!」
もつれ合うようにして、少年を乗せた自転車が二台駆け抜けた。
「一番土手に行く前に、私の通ってた小学校見に行かない?」
斎藤は和田の喉を見ながら言った。斎藤から行き先の提案とは珍しい。
「あっち」
指差す先に、少年たちの背がどんどん小さくなっていく。
「あっちね」
和田は斎藤の指を気にしている。力を入れて指差すとき、斎藤の人差し指は第一関節だけかすかに曲がる。
土手は半分が枯れ草で覆われていて、生えはじめのクローバーがまだらに侵食している最中だ。
「クローバーの花が咲くと、小学生の頃はみんなで冠作ったなあ」
「小学生かあ」
「土手を滑り降りて遊ぶんだけど、冬の間は枯れ草だから段ボールでもビニールでもよく滑るのね。でもクローバーが生えてくるとプラスチックのソリじゃなきゃだめなの」
「ほう」
「それも過ぎて、いろんな草がぼうぼうになると、またすごくすべりやすくなる」
「ほう」
「聞いてる?」
「もちろん、もちろん」
和田は、あのうなぎ屋は高いのだろうか。あとでこっそり覗いてみたい、そう考えている。うなぎ屋から誰か出てくるのが見える。一番土手に向かっているようだ。
何かにぶつかった。斎藤が立ち止っている。「あれ、高野のおじちゃんだ」
前からやってくるのは黄土色のつなぎを着た初老の男と十代中ごろの女だった。
「おや、斎藤さんのところの。お久しぶりです。お友達も、こんにちは」
頭を先に下げられてしまい、和田はあわてて会釈した。
「おじちゃん、何持ってるの?」
押している二台付き三輪車には大きなポリバケツが乗っている。
「見てごらん」
気安い様子で言葉を交わす二人を、少女と和田は手持ちぶさたで待っている。
げ。
と斎藤が和田に目配せをした。まわり込んでバケツを覗くと、赤いザリガニがわんさと入っている。
「実は今いなくなった亀を探していてね。昨日から罠を沈めているんだが、ごらんのとおり」
「亀ですか」
和田が思わず聞き返すと、彼は眉をあげた。
「そう。ほら美佳、ごあいさつしなさい」
「はじめまして、孫の美佳です」
「この子の亀が逃げ出してしまってね。小学校の亀池から、用水路から、巻上神社の池まで回ってるんだ。でもなかなかかからなくてね。ザリガニは鯉の餌にでもしようかな」
「美佳ちゃんと私は、遊んだことある……よね」
斎藤の物言いに遠慮を感じ、和田は訝しく思った。
「はい」
美佳はうなずく。
斎藤もほっとしたようにうなずき返す。
さきほどから、美佳の表情は全く動かない。
「せっかくだから、手伝おっか」
斎藤が言い出したので、和田も同意した。
「それで、今飼っている亀、どこで拾ったか覚えてないんです。酔っぱらって帰ってきて、そうだ、電話しよう、と思って出したら亀だったんです。」
和田の鉄板ネタなのだが、今日はあまりうけなかった。
「亀は買う人よりも拾う人の方が多そう」
斎藤の言葉に、和田は首をかしげたが、高野と美佳はうなずいた。
「そうなんですか?これはもう運命的だと思ってたんだけどなあ」
「運命的であることにはかわりないですよ」
高野はいたずらっぽく言った。
ポリバケツの中でザリガニがうごめいている音がする。